「長襦袢の襟が開いてしまう」を楽に解決する着付け方

長襦袢の襟が開いてしまう、詰まってしまう、襟が隠れてしまう、と困っている方は多いようです。
長襦袢の襟がきちんとしていると見た目にも美しいですね。
長襦袢を着たときにはきっちり合わせたはずなのに、着物を着ているうちにぐちゃぐちゃになっちゃうとよく言われます。崩れないように腰紐をどんどんきつく結ぶようになり、結果どんどん苦しくなってしまいます。悪循環です。
それは根本的に間違っています。
紐は体に押さえつけて止める道具です。それに対して体は動きます。紐をきつくすればするほど、元に戻らなくなり、どんどん気崩れます。上級者になれば、紐もだけでも上手く止められますが、初心者にはかなり難しいです。
山本流の着付けは楽で着崩れしません。
その最大の秘密は 長襦袢の着方にあります。
そのポイントは3つ
1、長襦袢はコーリンベルト一本
襟先2カ所と後ろ1カ所止めるだけです。
止めると三角形ができて安定的な形ができます。体も締め付けません。腰紐も伊達締めもなしです。胃の上は何もなくいくらでも食べられます。
2、ゴムなので、伸縮自由
体が動けば伸び、戻れば縮んで元通りになります。崩れないのではなく元へ戻る着付けなのです。
3、長い引っ張り布
着物は衣紋のカーブの美しさが魅力です。引っ張り布で下へ引っ張ることで実現します。
この引っ張り布を長くつけておくことによって、着物を着た時の腰紐で固定されるのです。

平安時代の十二単。襟元の美しさが際立ちます。
これは十二単の着付けの考え方の応用です。十二単では20枚も30枚も重ねて豪華さを競ったこともあるとか。
それを着付けする時に1枚1枚紐で止めていたら、紐でゴロゴロになってしまいます。
1枚着たら紐で止める、2枚目を着たら、紐で止める、3枚目を着たら1枚目の紐を抜き取って止める。これを繰り返すことによって、最後には紐は1本しか残りません。
長襦袢においても、引っ張りを長くしておけば、着物の紐で止まるので伊達締めも必要ありません。
さらに襟が詰まってきたときには、お手洗いで引っ張り布の先を引っ張れば襟が直接抜けます。
着付けは技術です。
どんなやり方を選ぶかが大切です。どこで習っても一緒ではありません。
長年、呉服屋として毎日着物を着て暮らしてきた母の経験値から生まれたシンプルで楽な着付けです。
山本流着付教室「装華塾」基礎コースが10月4日からオンラインで始まります。
こういった知恵がいっぱいの着付けをご自宅で学びませんか。
ブログの読者登録、こちらからできます
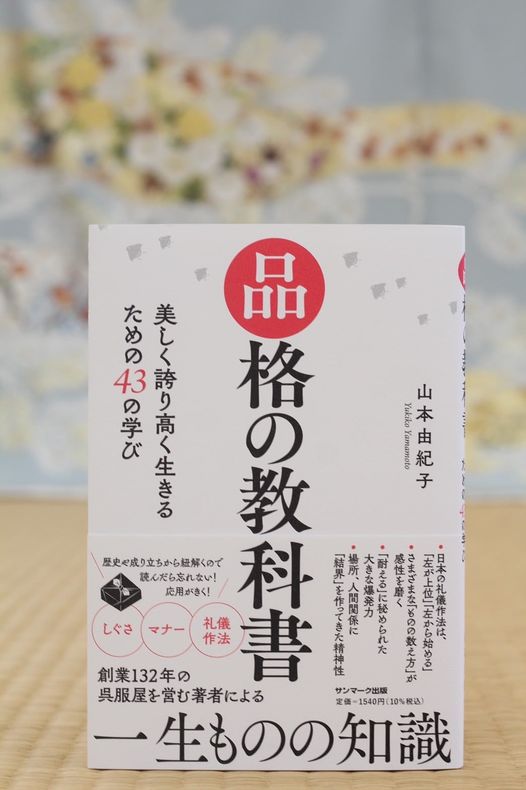
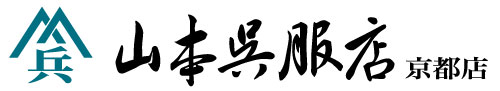

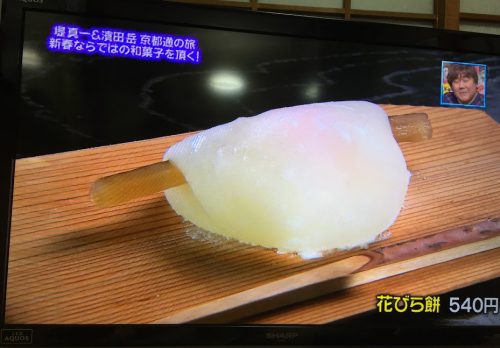








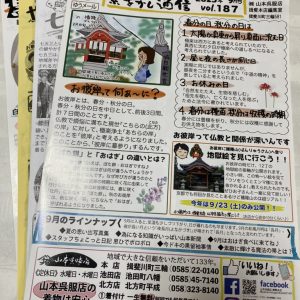

この記事へのコメントはありません。