「曽根崎心中」愛の形
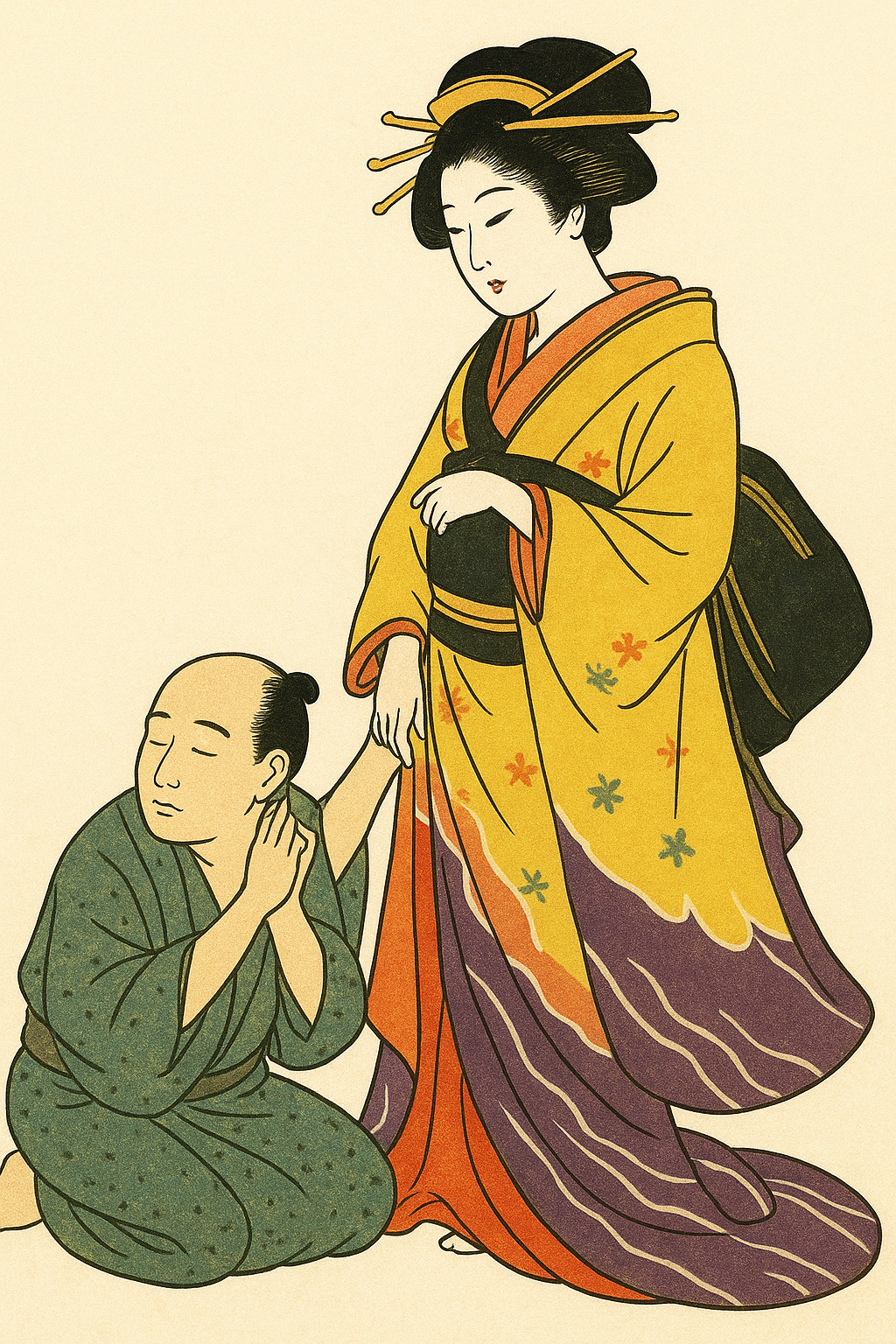
歌舞伎「曽根崎心中」の「天満屋の場」で、遊女お初が「死ぬ覚悟が聞きたい」と言って、他人にわからぬように下へ右足を差し出す。縁の下で隠れている醤油屋の手代(今で言う係長?)徳兵衛は足首をとって頬ずりして一緒に「自害する」と知らせる。
死に場所へ向かうために花道を急ぐ二人、映画「国宝」でも最後の見せ場になっていた。
「心中」とは、愛し合った男女が愛を貫くために一緒に死ぬこと。
江戸時代初期、実際に起きた心中事件を題材にした近松門左衛門の人形浄瑠璃『曽根崎心中』や『心中天網島』(しんじゅうてんのあみじま)などが大ヒットし、人気を博した。
私は心中が大嫌いだ。
心中モノが演目に入っていると、その間は誰もいないおでん屋さんでゆっくりおっちゃんと歌舞伎談義をしていた。
歌舞伎が大好きだった京都のお婆さんは夢見心地で「心中は最高の愛の形や」
死ぬことは永遠に一緒に生きようとすることだというのだ。
「死んでしまったら何もかも終わり」というのが私。
私はロマンチックなんてひとかけらもなく現実主義だった。
心中ブームに徳川幕府は躍起になって上演や本の出版を禁止した。
幕府にとって「忠義」は主君に対する服従や忠誠を誓うという最も大切な精神。
武士にとって「自分の命を犠牲にしても義理を果たすこと」が最高の証とした時代だった。
「心中」の言葉は「忠」を上下させたもの。
お初と徳兵衛の心中は、愛(自分の心)に対して忠実であったこと大問題だったのだ。
曽根崎心中の事件は、赤穂浪士が主君の仇討ちをして「忠義」を全うして切腹した直後。
武士でもない遊女と商人が使ったこともない刃物で死んだのも、ひょっとしたら赤穂浪士を真似て美しく死にたかったのではなかったかと考えられなくもない。
相変わらず、私は「心中モノ」が嫌いだ。
起こった事象に負けて「自分ではどうしようもない」「周りは変えられない」だから「死ぬしかない」などという考え方が嫌いだ。
お芝居の間中、オロオロと泣き叫び、死へと逃げるとしか思えないあらすじをじっと見ている趣味はないのだ。
[関連記事]
映画「国宝」のポスターに懐かしく、、
襲名披露
ブログの読者登録、こちらからできます
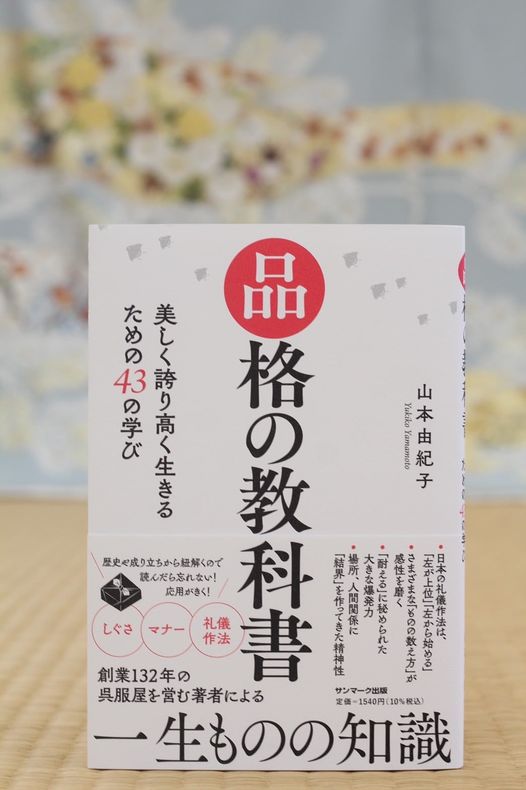
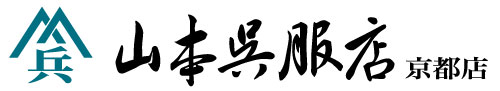


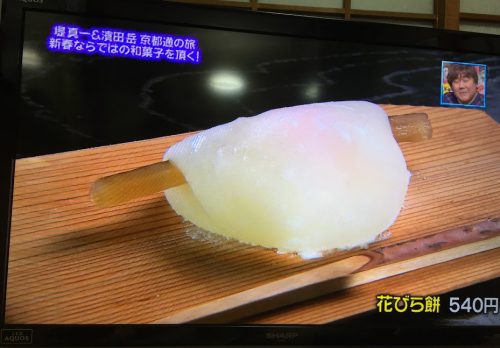





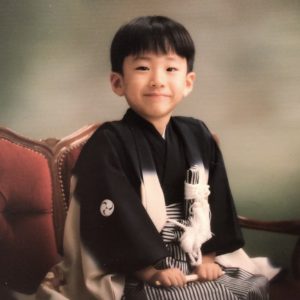


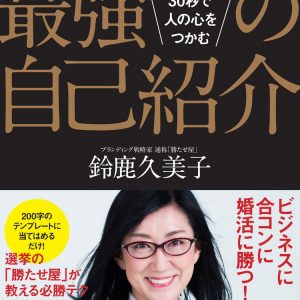
この記事へのコメントはありません。